こんにちは。
東京ビジネス外語カレッジ(TBL)校長の小林司朗です。
今回は、少し“本の話”から始めたいと思います。
私がこれまで繰り返し読み、何度も自分自身の仕事や人生の軸に立ち返ってきたシリーズがあります。
それが、ジム・コリンズ著『ビジョナリー・カンパニー』シリーズ。
世界中の経営者・教育者が指南書として読み継ぐ、企業研究の名著です。
けれど、これは決して“経営の本”ではありません。
高校生の皆さんや、保護者の方々にもきっと響く、人生の選択や生き方に役立つ本(全4巻)です。
『ビジョナリー・カンパニー』シリーズとは?
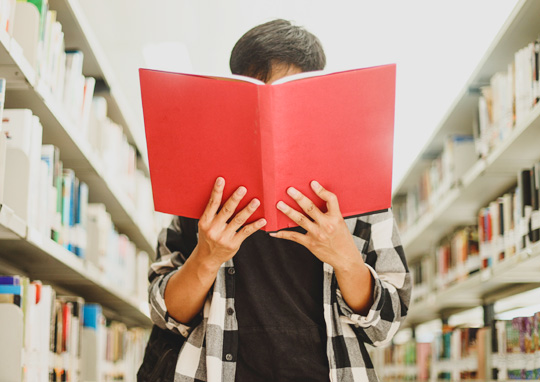
このシリーズは、アメリカの経営学者ジム・コリンズ氏が、数十年におよぶ企業のデータを分析し、「なぜ一部の企業は成功し続け、他の企業は衰退していくのか?」を探求したものです。
たとえば第1巻・第2巻では、
- 3M、ジョンソン&ジョンソン、ウォルト・ディズニー、ソニーなど、長期的に成長し続ける企業
- 一方で、一時的には話題になっても、文化や価値観を見失って衰退していった企業
この両者を比較しながら、**一時的な成功ではなく、永続的な成長を可能にする“本質的な力”**を明らかにしていきます。
表面的な成功の法則と、本当の成功の法則

このシリーズでは、多くの人が信じがちな“成功の常識”が、次々と否定されていきます。
たとえば…
- カリスマ性のあるリーダーがいる企業は強い? → NO
- スピード命で突き進む企業が勝つ? → NO
- トレンドに乗れば生き残れる? → NO
本当に偉大な企業に共通していたのは、
- 謙虚で、粘り強く、ぶれないリーダー
- 変わるべきところは変え、守るべきものは守り続けた組織文化
- 派手ではなくても、日々コツコツ続ける実行力
つまり、“一瞬の成果”ではなく、“長く続く力”を大事にしていたのです。
ソニーはなぜ復活できたのか?
たとえばソニー。
日本を代表するグローバル企業として知られながら、かつてはブランド力や技術の優位性を見失い、停滞した時期がありました。
しかし、創業時の精神に立ち返り、組織改革と挑戦を重ねることで、
再びグローバル市場のトップランナーとして存在感を取り戻しています。
この復活の裏側には、『ビジョナリー・カンパニー③ 衰退の五段階』にも通じる視点があります。
「衰退は運命ではない。気づき、見直し、行動すれば、必ず立て直せる」
不確実な時代に必要な「選び方」と「進み方」
第4巻『自分の意志で偉大になる』では、変化の激しい時代に成功し続けた企業の共通点が語られています。
- 10マイル行進(どんな日でも、決まった距離を着実に進む)
- 弾丸を撃ってから大砲を撃て(まずは小さく試す)
- 第20マイルルール(短距離走ではなく、継続の力)
それはつまり、**スピードよりも「正しい方向」と「続ける力」**こそが生き残りのカギだということです。
人生も『ビジョナリー・カンパニー』になれる

私はこの本を読むたびに思います。
これは、企業の話ではなく“私たち自身の人生”に通じる話だ、と。
- 将来、どんな仕事に就くのか?
- どんな人生を送りたいのか?
- どんな自分でいたいのか?
それらはすべて、「自分という会社をどう経営していくか」という問いそのものです。
高校生のみなさんも、保護者のみなさまも、自分の価値観、行動、習慣、選択を積み重ねながら、“自分だけのビジョナリー・カンパニー”を育てているのです。
TBLで育つ「永続する力」
TBLでは、単に英語やビジネススキルを教えるだけではありません。
- 「自分の軸」を見つける
- 「ブレずに続ける力」を育てる
- 「変わるべき時に、勇気を持って変わる力」を学ぶ
それらを、実践の中で体得していく場所です。
最後に|少し難しいけれど、きっと役に立つ一冊です
「ビジョナリー・カンパニー」シリーズは、たしかに高校生にとっては少し難しいかもしれません。
でも、今すぐ読まなくても大丈夫です。
TBLでは、そこに書かれているような大切な考え方を、日々の授業や挑戦の中で自然と学んでいくことができます。
TBLでは、進路のその先にある“人生の経営”を意識した学びを提供しています。
オープンキャンパスでは、在学生や教職員とのリアルな対話も体験していただけます。
一瞬の成功より、“続けられる自分”になる。
TBLは、あなたが“自分という会社”を育てる力を身につける場所です。
校長プロフィール
小林 司朗(こばやし しろう)
東京ビジネス外語カレッジ校長 / WEWORLDグループCOO/デンバー大学大学院(Daniel College of Business)会計学修士(Macc)・情報技術学修士(MSIT)/教育、経営、哲学を横断しながら、“人と社会のポテンシャル”を引き出すための仕組みづくりに取り組む。専門学校から企業・国家レベルにまで視野を広げ、「越境する学び」と「実践知の再設計」を軸に、次世代教育モデルの実装を目指している。


