今日は12月1日!いよいよ今年もクリスマスの季節がやってまいりました。

ご家族や友人とのパーティー、華やかなイベントに参加される方も多いのではないでしょうか。
「元々は海外の行事、クリスマスなんて…」と個人的には少し否定的に思っていましたが、別の視点で考えてみると、海外へ出る方にとって自国の文化について知るのは良い事かもしれない、と思いこの度日本でのクリスマスについて調べてみました。

今回は、日本のクリスマスの歴史にスポットを当てて、ご紹介します!
日本で最初のクリスマス
日本でのクリスマスの始まりと言われているのは、有名なカトリック教会の宣教師フランシスコ・ザビエルが日本に上陸した1549年と言われています。
ただ他説もあり、カトリック教会の別の宣教師が日本人の信徒を招いて現在の山口県でミサを行った1552年という説もあります。

しかし、ご存知のとおりその後は江戸幕府のキリスト教の禁止により、長い期間、公にはならない行事だったようです。
明治にはクリスマス商戦開始!
その後クリスマスが多くの人々に知れ渡ったのは、1873年のキリシタン放環令が出た明治時代以降となります。
1900年頃に銀座の明治屋(小売店)が進出、クリスマス商戦が始まったことがきっかけだそうです。

今も有名な不二家、三越、帝国ホテルなどが早い時期から参加していたようです。
クリスマスが大正天皇祭と同じ日で定着
昭和に入り、大正天皇が崩御した12月25日が「大正天皇祭」として休日に設定されました。
クリスマスの日が日本の休日だったこの時代に多くの家庭に行事が普及し、習慣となっていったようです。
1948年に「大正天皇祭」は休日から外されてしまったものの、以降もクリスマスは日本の年中行事として誰もが知るものとなっています。

昨今では10月末のハロウィンが終わるとすぐに街の中の看板やサインがクリスマス仕様に変わりますし、11月の上旬からクリスマスツリーやイルミネーションで飾られた商業施設なども見かけますよね。
欧米のクリスマス文化
欧米では、クリスマスシーズンは様々な人にプレゼントを買ったり、グリーティングカード(クリスマスカード)を送ったりと、大忙しです。
私も留学中はホストファミリーの一人ひとりへプレゼントを選ぶのがとても楽しかったです。

ちなみに年賀状は元旦から数日の間に届くのがマナーですが、クリスマスカードはクリスマスの前に到着するのがベストです!
欧米では、11月末から順次届くクリスマスカードを、部屋に飾り、クリスマスの飾り付けの一部にして楽しみます。
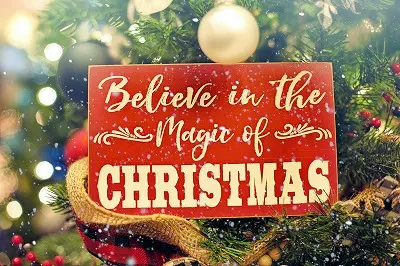
ちなみに、キリスト教の教会は一般的に、キリスト教徒でない人へも開放されていて、教徒でない人もクリスマスの礼拝に出席することが可能な場合もあるそうです。
留学した際は、近くの教会で本場のクリスマスの過ごし方を体験してみるのも良いかもしれません。
まとめ
今回は、日本のクリスマスの歴史について、ご紹介しました!
日本のクリスマスの歴史は思っていたよりもずっと古く驚きました。
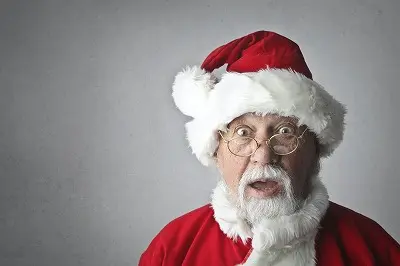
こういった背景を知ることで皆さんがイベントをより楽しむ事が出来れば嬉しく思います!

